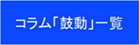「鼓動」2010年8月30日
巨峰の誕生
 葡萄の王様、巨峰。
葡萄の王様、巨峰。粒が大きく、香りがよいことで人気があり、日本で最も多く生産されている。
国内で葡萄栽培が本格化したのは、明治時代に入ってから。高品質で、雨が少なく乾燥にも強い、ヨーロッパ品種の栽培は、雨が多く、寒暖の差が大きい日本での栽培は難しかった。そのため、アメリカ品種やオーストラリア品種など、日本の気候でも育ちやすい品種との交配が進められることとなった。
昭和に入ると、静岡県在住の大井上康という民間の葡萄研究学者によって、日本に古くからある「石原早生」に、オーストラリアのぶどう「センテニアル」を交配した研究が進められ、昭和17年に一房の新種が誕生した。品種名「石原センテニアル」、巨峰の誕生だ。
やがて、日本は戦中・戦後の食糧不足と米・麦を主体とした食糧体制が敷かれ、贅沢品とされる果物、巨峰の栽培が陽の目を見ることなく、昭和27年、大井上康はこの世を去る。
昭和31年、大井上康の弟子だった越智通重が福岡県田主丸に誕生した「九州理農研究所」の所長に就任。国内はもとより、台湾、ブラジルなどからも研究生がやってくる。
昭和33年、いよいよ田主丸の地に巨峰の開植がおこなわれる。やがて、葡萄園は、見事な実をつけ、巨峰の栽培に始めて成功する。
その後、「九州理農研究所」は「果実文化協会」を立ち上げ、専門誌「果実文化」を発行。購読者は、九州一円にとどまらず、北海道、韓国、台湾にも広がっていった。多くの出版物が東京で発行されていた時代に、片田舎の町から、国内外へ情報発信される出版物だった。
いよいよ葡萄狩りのシーズン到来。長雨の影響で生育が心配されたが、今年もまずまずの出来だそうだ。(K)
 新型コロナウイルス感染症対策が各地で実施されています。イベント・店舗の運営状況は公式サイト等でご確認ください。
新型コロナウイルス感染症対策が各地で実施されています。イベント・店舗の運営状況は公式サイト等でご確認ください。