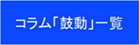「鼓動」2010年10月6日
秋刀魚の歌
 今年のサンマは、不漁が続いて高値が続いていたが、9月の下旬となってようやく漁が戻って、平年並みに価格も落ち着いたようだ。秋分の日、我が家の夕食の主役はサンマだった。サンマにはカボスの果汁を滴らせ、そろそろ辛味ののり始めた大根おろしも添えられた。
今年のサンマは、不漁が続いて高値が続いていたが、9月の下旬となってようやく漁が戻って、平年並みに価格も落ち着いたようだ。秋分の日、我が家の夕食の主役はサンマだった。サンマにはカボスの果汁を滴らせ、そろそろ辛味ののり始めた大根おろしも添えられた。 サンマが秋の味覚として広く知れ渡ったのは、大正になってからのことらしい。 漁法が発達して、漁獲量が増えたことで、庶民の食卓に上るようになった。「あはれ 秋風よ 情あらば伝えてよ」とはじまる佐藤春夫の「秋刀魚の歌」の登場もサンマが庶民の味として広まったことの反映だろう。
かつては、表通りから裏路地に入れば、家々の勝手口の近くでサンマを焼く光景にぶつかった。どこの家庭でも七輪の上に金網を載せ、サンマを並べて焼いていた。サンマの脂は炭に滴り落ち、もくもくとけぶり、サンマを燻した。夕暮れの気配とともに、あたりに立ち込める煙と匂い。遊び呆けていた少年たちもそろそろ帰宅しなければならない気持ちになったものだ。
サンマの記憶は、昭和の暮らしの記憶に結びついてどこかノスタルジックだ。(HR)
 新型コロナウイルス感染症対策が各地で実施されています。イベント・店舗の運営状況は公式サイト等でご確認ください。
新型コロナウイルス感染症対策が各地で実施されています。イベント・店舗の運営状況は公式サイト等でご確認ください。