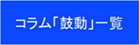「鼓動」2010年12月3日
ヴィヨンの妻
 昨年は、太宰治生誕100周年ということもあって、太宰治の本はずいぶん読まれたようだ。特に若い世代には、相変わらず根強い人気を誇っている。映画の方も『ヴィヨンの妻』が公開されていたが、あいにく見る機会を逸してしまった。
昨年は、太宰治生誕100周年ということもあって、太宰治の本はずいぶん読まれたようだ。特に若い世代には、相変わらず根強い人気を誇っている。映画の方も『ヴィヨンの妻』が公開されていたが、あいにく見る機会を逸してしまった。小説『ヴィヨンの妻』は、戦後直後の混乱の時期を背景に、借金や浮気を繰り返す詩人と妻の物語である。やり切れぬ虚無感を抱く無頼の徒である詩人は、飲んだくれの日々を送っているがある日なじみの居酒屋で売り上げの金を盗む。家まで押しかけてきた居酒屋の主人夫婦に金を返すよう迫られるが、詩人は逃げ出してしまう。残された妻に返済の当てなどない。途方に暮れた妻は家を出てさまよううちに、電車の広告に、夫の名前とともに、彼が書いた評論の題名を見つける。題名には「フランソワ・ヴィヨン」の名前があった。
フランソワ・ヴィヨンは、15世紀のフランスに実在した詩人で、パリ大学を卒業したが、乱闘騒ぎで司祭を殺してしまい、パリを逃亡し窃盗団に加わる。盗みの罪によって幾度か投獄されるが、最後にはパリから追放されてその後の行方は分からなくなっている。もちろん、妻は、ヴィヨンについていささかも知らないのだが、わけもわからないまま涙がこぼれる。
妻を通して語られる独白の文体のリズムは、太宰特有のものだ。巧みな語り口は軽妙でよどみがない。せっぱつまった妻が、やがて覚悟を決め、一種の開き直りのような生き方に変わってゆくのは、戦後の混乱を反映しているのか、それともそもそも女というものが逞しいのか、よくわからない。
破滅型の詩人とその妻。家庭内での距離は近くて遠い。あるいは遠くて近い。二人の会話は不思議な味わいが漂う。太宰にとって、人が生きてゆく上で、どれほどの倫理が必要なのかは、ある意味切実だったのだろう。本来太宰は倫理観の強い人物だったのかもしれない。が、その生き方は逆説的なほど反倫理的なものであり、まるで滅び急いだかのようだ。『ヴィヨンの妻』は、振幅の大きかった太宰晩年の、一閃の光芒ともいうべき作品となっている。
(IK)
 新型コロナウイルス感染症対策が各地で実施されています。イベント・店舗の運営状況は公式サイト等でご確認ください。
新型コロナウイルス感染症対策が各地で実施されています。イベント・店舗の運営状況は公式サイト等でご確認ください。