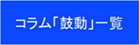「鼓動」2010年12月16日
冬至
 767年、杜甫は、四川省の長江沿岸奉節に滞在している。齢は、すでに50代後半。この地で二度目の冬至を迎えた杜甫は、憂愁に満ちた七言律詩「冬至」を作っている。書き出しの2行から、すでに重苦しい。
767年、杜甫は、四川省の長江沿岸奉節に滞在している。齢は、すでに50代後半。この地で二度目の冬至を迎えた杜甫は、憂愁に満ちた七言律詩「冬至」を作っている。書き出しの2行から、すでに重苦しい。年々 至日 長(つね)に客と為る
忽忽として 窮愁(きゅうしゅう) 人を泥殺(でいさつ)す
詩のあらかたの意味は次のようになる。今年もまた、冬至の日を、旅人のままでいる。失意のまま、困窮と愁いがまとわりついて、もはやずたずたの気分だ。長江のほとりですっかり老け込み、遠い異郷の地の風俗にも慣れしたんだ。雪があがって、こうして赤茶けた谷間を見下ろしている今頃、紫宸殿では冬至の参賀も終わり、官僚たちは退出したことだろうな。そんなことを思っていると、心はすっかり折れてしまって、都がどちらにあるのかさえわからなくなる。
懐かしい都を偲ぶ歌にも、老残の嘆きが色濃い。放浪の果て、「冬至」の詩から3年後、杜甫は旅の途中で亡くなっている。けれど、国を憂い、民衆の苦しみを詠じた放浪の詩人杜甫は、死後も、彼の詩を愛する人の心の中で、いつまでもさすらっている。(IK)
 新型コロナウイルス感染症対策が各地で実施されています。イベント・店舗の運営状況は公式サイト等でご確認ください。
新型コロナウイルス感染症対策が各地で実施されています。イベント・店舗の運営状況は公式サイト等でご確認ください。