- ホーム
- 特集
- 特集 福岡マンホール図鑑 "街にあふれる足下アート"
- 特集 福岡マンホール図鑑 有識者 薄毛の髭のっぽ氏インタビュ...
特集 福岡マンホール図鑑 有識者 薄毛の髭のっぽ氏インタビュー

今回の特集記事を実施するにあたり、日本のマンホール業界における有識者の話は欠かせないということで、ウェブサイト「日本マンホール蓋学会」のサポートメンバーの1人である薄毛の髭のっぽ氏にオファー。日本中のマンホールを見て来た氏の視点で、福岡のマンホールの特徴や魅力、マンホールにかける情熱などを聞いた。
――薄毛の髭のっぽさんとマンホールとの出会いは?
薄毛の髭のっぽ:以前、熊本県八代市の「東陽 石匠館」という石橋資料館を訪ねたことがあったのですが、たまたま雨が降っており傘をさして足元を見ながら歩いていると、マンホール蓋に「石橋」が描いてあり、その美しさに目を奪われました。これがマンホールとの初めての出会いでした。
――マンホールにハマったキッカケは?
在住の地や近在のマンホールを見ると、各市町村それぞれに絵柄が違い、その理由を調べ始めると各々にストーリーがあって、その面白みにどんどんのめり込んでいきましたね。
――福岡のマンホールの特徴は?
特に全国各地のデザイン蓋との絵柄選定に差異は見受けられませんが、古賀市の蓋のように下水処理場そのものがデザインされたものは、他に見当たりませんね。(古賀市のマンホールはコチラ)
――マンホールファン必見のマンホールを教えてください。
福岡県久留米市城島町に敷設されている「酒樽と鬼瓦」絵のカラーデザイン蓋はオススメです。地元特産のお酒と下水の組み合わせが何ともユニークなんですよ。(久留米市のマンホールはコチラ)
――印象に残っているマンホールは?
福岡県大川市の蓋絵には、下水道敷設当時の下水道担当部署の人数が筑後川の特産魚「えつ」の数で表してあります。なかなか面白い裏話だったので、とても印象に残っていますね。(大川市のマンホールはコチラ)
――全国にどれだけの種類のマンホールがありますか?
正確な数は把握していないですが、デザイン蓋だけで3400種ほどはありそうです。現在(平成の大合併後)の全国市町村数1744に対して、そのほぼ倍の数となります。ただ、規格模様の蓋もありますので、その実態は不詳です。
――マンホールファン予備軍に向けてマンホールの魅力、楽しみ方を教えて下さい。
直径60cmの蓋の中に、耐滑り性や耐摩耗性を考慮しながら、その土地や地域の特徴(名所・旧跡・特産品・名産品・風習・歴史景観等々)を一目で解かるようにデザインされていますので、気楽な郷土調べというか、その土地を旅した気分を楽しむことができると思います。また、描かれている場所を実際に訪ねてみるのも面白いでしょうね。ホームページ「日本マンホール蓋学会」では、単に各地の蓋を県市町村別に掲載するだけではなく、全国の蓋の絵柄を分類整理して公開しているので、同じ絵柄の描き方の違いなども見ることができますよ。
――マンホールが楽しめるイベントなどがあれば教えてください。
毎年9月10日は「下水道の日」として、全国の各市町村単位でデザインマンホールの展示やデザイン募集などの各種イベントが行われていたりしますし、他に毎年7月末には「下水道展」が行われます。詳細はインターネットなどで検索してしてみるのが良いかもしれませんね。
――最後に読者に一言。
4000年前の古代インドで作られたとされる下水道=「衛生的な生活」を営むためのインフラですが、人々が目を背けたがる下水事業に、そのマンホール蓋に絵をデザインして、この事業に注目してもらおうという先人の叡智と発想に感心しますし、世界で他に類を見ない「日本文化のすばらしさ」の一つでもあります。また、消火栓用とか上水道用なんかにも絵柄があるものがありますので、非常に奥が深い世界です。ぜひ皆さんも一度マンホールの世界をのぞきに来てはいかがでしょうか。
薄毛の髭のっぽ:以前、熊本県八代市の「東陽 石匠館」という石橋資料館を訪ねたことがあったのですが、たまたま雨が降っており傘をさして足元を見ながら歩いていると、マンホール蓋に「石橋」が描いてあり、その美しさに目を奪われました。これがマンホールとの初めての出会いでした。
――マンホールにハマったキッカケは?
在住の地や近在のマンホールを見ると、各市町村それぞれに絵柄が違い、その理由を調べ始めると各々にストーリーがあって、その面白みにどんどんのめり込んでいきましたね。
――福岡のマンホールの特徴は?
特に全国各地のデザイン蓋との絵柄選定に差異は見受けられませんが、古賀市の蓋のように下水処理場そのものがデザインされたものは、他に見当たりませんね。(古賀市のマンホールはコチラ)
――マンホールファン必見のマンホールを教えてください。
福岡県久留米市城島町に敷設されている「酒樽と鬼瓦」絵のカラーデザイン蓋はオススメです。地元特産のお酒と下水の組み合わせが何ともユニークなんですよ。(久留米市のマンホールはコチラ)
――印象に残っているマンホールは?
福岡県大川市の蓋絵には、下水道敷設当時の下水道担当部署の人数が筑後川の特産魚「えつ」の数で表してあります。なかなか面白い裏話だったので、とても印象に残っていますね。(大川市のマンホールはコチラ)
――全国にどれだけの種類のマンホールがありますか?
正確な数は把握していないですが、デザイン蓋だけで3400種ほどはありそうです。現在(平成の大合併後)の全国市町村数1744に対して、そのほぼ倍の数となります。ただ、規格模様の蓋もありますので、その実態は不詳です。
――マンホールファン予備軍に向けてマンホールの魅力、楽しみ方を教えて下さい。
直径60cmの蓋の中に、耐滑り性や耐摩耗性を考慮しながら、その土地や地域の特徴(名所・旧跡・特産品・名産品・風習・歴史景観等々)を一目で解かるようにデザインされていますので、気楽な郷土調べというか、その土地を旅した気分を楽しむことができると思います。また、描かれている場所を実際に訪ねてみるのも面白いでしょうね。ホームページ「日本マンホール蓋学会」では、単に各地の蓋を県市町村別に掲載するだけではなく、全国の蓋の絵柄を分類整理して公開しているので、同じ絵柄の描き方の違いなども見ることができますよ。
――マンホールが楽しめるイベントなどがあれば教えてください。
毎年9月10日は「下水道の日」として、全国の各市町村単位でデザインマンホールの展示やデザイン募集などの各種イベントが行われていたりしますし、他に毎年7月末には「下水道展」が行われます。詳細はインターネットなどで検索してしてみるのが良いかもしれませんね。
――最後に読者に一言。
4000年前の古代インドで作られたとされる下水道=「衛生的な生活」を営むためのインフラですが、人々が目を背けたがる下水事業に、そのマンホール蓋に絵をデザインして、この事業に注目してもらおうという先人の叡智と発想に感心しますし、世界で他に類を見ない「日本文化のすばらしさ」の一つでもあります。また、消火栓用とか上水道用なんかにも絵柄があるものがありますので、非常に奥が深い世界です。ぜひ皆さんも一度マンホールの世界をのぞきに来てはいかがでしょうか。
薄毛の髭のっぽ プロフィール
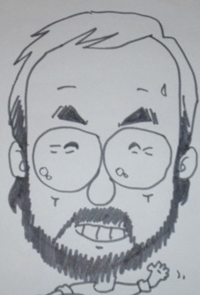 1950年9月福岡市生まれののっぽ(身長184cm)、体重はちょっと重めの83キロ。
1950年9月福岡市生まれののっぽ(身長184cm)、体重はちょっと重めの83キロ。2011年に還暦を迎え、40年あまり勤めた会社を定年退職後、3ヶ月間 走行距離2万kmの日本一周車旅を敢行。
若い頃からの喫煙習慣を2012年1月、朝の一服が不味かったことをきっかけにキッパリと止める。
血統的に飲酒には強く、種類を選ばず、また止めるつもりもない。
毎日が日曜日で自由時間はたっぷり保有し、あらゆることに興味津々の気持ちを持ち続けたいと思っている。
楽しいことなら何でもやりたいし、笑える場所なら何処へでも行く(とある歌の歌詞からパクリです)スタイル。
また、読書が大好きで、昨年は「古事記」の本3種類を読破し、250柱を超える神々の系譜と神話、ゆかりの神社を1枚の大きなパネルに一纏めに(http://tabitoroman.blog.bbiq.jp/blog/KJ1.html)。
旅、スポーツ(最近はもっぱらゴルフと週2回のミニバレーボール)、釣り虹鱒のルアー釣り等々趣味は多く、パソコンも好き。
福岡県の蓋写真を繋いで動画もどきを作成してyoutubeにも載せてみました(http://tabitoroman.blog.bbiq.jp/blog/FKK.html)。
最近は、マンホール蓋の写真撮影にはまっている。
■日本マンホール蓋学会
http://sky.geocities.jp/usagigasi1f/
 新型コロナウイルス感染症対策が各地で実施されています。イベント・店舗の運営状況は公式サイト等でご確認ください。
新型コロナウイルス感染症対策が各地で実施されています。イベント・店舗の運営状況は公式サイト等でご確認ください。













