- ホーム
- JAPAN! JAPAN! JAPAN!
- 第4回 オタクは世界を変えることができるか? 中国のオタクが...
第4回 オタクは世界を変えることができるか? 中国のオタクが教えてくれたこと
「櫻井さんはオタクのオタクなんだよね」友人の若いオタク日本人女子が、そのまた友人に私のことをこう話した。
名言だと思った。そう、たしかに、私はオタクのオタクだ。
オタクも、カワイイと同じように、21世紀に入ってとくに世界語化していった言葉だろう。と同時に、その意味もまた従来多くの日本人が感じていた雰囲気から拡大し、変わり始めている。私は、そんなオタクたちに、これからの未来の大きな可能性を感じているし、希望を託していると言ってもよいだろう。
名言だと思った。そう、たしかに、私はオタクのオタクだ。
オタクも、カワイイと同じように、21世紀に入ってとくに世界語化していった言葉だろう。と同時に、その意味もまた従来多くの日本人が感じていた雰囲気から拡大し、変わり始めている。私は、そんなオタクたちに、これからの未来の大きな可能性を感じているし、希望を託していると言ってもよいだろう。
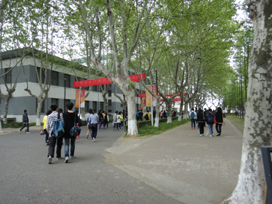 ▲南京信息行程大学。緑がいっぱいの広大なキャンパス。
▲南京信息行程大学。緑がいっぱいの広大なキャンパス。 ▲私の講義で質問をする自称オタク女子大生。アニメもゲームも音楽も日本のものが大好き。
▲私の講義で質問をする自称オタク女子大生。アニメもゲームも音楽も日本のものが大好き。世界の人たちがお互いを理解しあうのは本当に難しい。テレビや新聞を見れば、そこには争い合う世界がつねに映しだされている。だが、世界の明るい未来を希望しない人はいないと私は信じている。
では、どうすればよいのか? そのための方法がいくつあっても問題はないだろう。私が外交は政治家や官僚だけがするものではないと考えている理由はそこにこそある。 私たち一人ひとりが言ってみれば外交官なのだ。自分の国を好きになってもらい、相手の国を好きになる。そんな個々の日常のつながりこそが世界を変えていくと私は信じてやまない。
2010年1月、私はそれまで封印してきた中国での文化外交活動を本格的にスタートさせた。2007年から開始していた文化外交活動だが、日本から遠い国で文化外交に関する私なりの方程式のようなものが見えた段階で、改めて隣国であり、さまざまな課題を抱えている中国との関係を考えたいと思っていたからだ。
そんな私が最初の訪問地、北京で出会ったのが、まさに中国のオタクたちだった。
では、どうすればよいのか? そのための方法がいくつあっても問題はないだろう。私が外交は政治家や官僚だけがするものではないと考えている理由はそこにこそある。 私たち一人ひとりが言ってみれば外交官なのだ。自分の国を好きになってもらい、相手の国を好きになる。そんな個々の日常のつながりこそが世界を変えていくと私は信じてやまない。
2010年1月、私はそれまで封印してきた中国での文化外交活動を本格的にスタートさせた。2007年から開始していた文化外交活動だが、日本から遠い国で文化外交に関する私なりの方程式のようなものが見えた段階で、改めて隣国であり、さまざまな課題を抱えている中国との関係を考えたいと思っていたからだ。
そんな私が最初の訪問地、北京で出会ったのが、まさに中国のオタクたちだった。

「中国の大学はオタクの温床ですよ」 そんなふうに明るく語りながら、私も知らないアニメ談義を次々に繰り出す彼らと語り明かしながら、中国という国と私の距離がいっきに近くなるのを感じていた。彼らの日本という国への関心や愛は私の想像をはるかに超えて深かったのだ。
友達を作る。これ以上の外交はないのではないかとさえ思わせてくれる彼らとの出会いだった。
彼らは、夏冬のコミケともなるとよく東京にやってくる。そんなときは、アニメや音楽業界、友人のオタクたちまで、私の友人たちと彼らとのコミュニケーションをとれる機会をできるかぎり作ってきた。「コミケ飲み」と呼んでいる飲み会の出席者が一様に、2010年1月の北京での私と同じように感じてくれているのは嬉しいかぎりだ。ファッションショーなどの大型イベント企画もやりがいがあるのだが、こんな草の根の文化外交活動が私は大好きだ。
友達を作る。これ以上の外交はないのではないかとさえ思わせてくれる彼らとの出会いだった。
彼らは、夏冬のコミケともなるとよく東京にやってくる。そんなときは、アニメや音楽業界、友人のオタクたちまで、私の友人たちと彼らとのコミュニケーションをとれる機会をできるかぎり作ってきた。「コミケ飲み」と呼んでいる飲み会の出席者が一様に、2010年1月の北京での私と同じように感じてくれているのは嬉しいかぎりだ。ファッションショーなどの大型イベント企画もやりがいがあるのだが、こんな草の根の文化外交活動が私は大好きだ。
女子大生たちに思い思いのカワイイポーズをとってもらう





2012年4月、私は南京を訪ねた。前々回の本連載で書いた南京信息工程大学(Nanjing University of Information Science & Technology)で授業するためである。
カワイすぎる南京の大学教師の人生を変えたのは「スラムダンク」とセーラー服
ここでも日本を愛してくれるオタク学生たちに出会った。世界の若者がオタクと口にするとき、そこには日本のクリエイティブ(とくにアニメやマンガ)に詳しいという意味が含まれている。言ってみれば、私は日本が好きですよ、関心を持っていますよと公言してくれているようなものなのだ。彼らの日本への好意や関心が最初はアニメやマンガだったとしても、そこに描かれている日本社会や、それを創りだした日本という国への関心を端緒に、彼らは日本という国自体に深い愛情を注ぐようになってくれるのが一般的だ。
そのいっぽう日本でアニメ文化外交の話をするとき、ときどき出てくるのが「私はアニメを見ないんで」という意見だ。私は、アニメやマンガを好きになることが重要だとは一言も言っていない。それは個人の問題だ。私は、アニメやマンガを通して日本に好意を持ってくれた世界の人たちの気持ちに、日本人がもっと寄り添ってもよいのではないだろうかということを言いたいだけなのである。彼らは日本にとっても日本経済にとっても、宝物のような存在だ。そのことを理解しているか、していなかで、私はこれからの世界と日本の関係は大きく変わってくるとさえ思っている。
話を南京のオタク大学生たちに戻そう。
私の講義を熱心に聞いてくれた学生の中には、セーラー服を着ている学生もいた。とくに珍しいことではないそうだ。ちなみに全員20歳を超えている。
カワイすぎる南京の大学教師の人生を変えたのは「スラムダンク」とセーラー服
ここでも日本を愛してくれるオタク学生たちに出会った。世界の若者がオタクと口にするとき、そこには日本のクリエイティブ(とくにアニメやマンガ)に詳しいという意味が含まれている。言ってみれば、私は日本が好きですよ、関心を持っていますよと公言してくれているようなものなのだ。彼らの日本への好意や関心が最初はアニメやマンガだったとしても、そこに描かれている日本社会や、それを創りだした日本という国への関心を端緒に、彼らは日本という国自体に深い愛情を注ぐようになってくれるのが一般的だ。
そのいっぽう日本でアニメ文化外交の話をするとき、ときどき出てくるのが「私はアニメを見ないんで」という意見だ。私は、アニメやマンガを好きになることが重要だとは一言も言っていない。それは個人の問題だ。私は、アニメやマンガを通して日本に好意を持ってくれた世界の人たちの気持ちに、日本人がもっと寄り添ってもよいのではないだろうかということを言いたいだけなのである。彼らは日本にとっても日本経済にとっても、宝物のような存在だ。そのことを理解しているか、していなかで、私はこれからの世界と日本の関係は大きく変わってくるとさえ思っている。
話を南京のオタク大学生たちに戻そう。
私の講義を熱心に聞いてくれた学生の中には、セーラー服を着ている学生もいた。とくに珍しいことではないそうだ。ちなみに全員20歳を超えている。

「高校生のとき着て学校に行きたかったけど、できなかったら今している」簡単に言えば、そういうことだ。
コスプレで授業を受けることもあるのだそうだ。アニメーションやゲームのクリエイターを育成する芸術系の大学ということもあってか、学内の雰囲気も教師サイドも「その何が問題になるの?」といった雰囲気である。
夜は、大学の先生や彼女たちと近くのカラオケに繰り出した。
彼女たちは最近の日本のJ POPのヒット曲を次々に歌った。彼女たちから日本の最近のヒット曲を逆に私が教わるありさまだったが、この展開は私の訪中ではとくに珍しいことではない。
コスプレで授業を受けることもあるのだそうだ。アニメーションやゲームのクリエイターを育成する芸術系の大学ということもあってか、学内の雰囲気も教師サイドも「その何が問題になるの?」といった雰囲気である。
夜は、大学の先生や彼女たちと近くのカラオケに繰り出した。
彼女たちは最近の日本のJ POPのヒット曲を次々に歌った。彼女たちから日本の最近のヒット曲を逆に私が教わるありさまだったが、この展開は私の訪中ではとくに珍しいことではない。
KTV(カラオケボックス)で次々にJ POPを熱唱する教師と生徒




南京滞在中、私は結局誰ひとり日本人に会わなかった。だが、周囲にはいつも「日本」があった。
こんな体験を自分だけでしているのはいつももったいないと思っている。みなさんも世界にある、いま私たちに見えていない「日本」を探しにいきませんか?それは意外なほど簡単に見つかるし、日本のクリエイターたちがしてきたことはそれだけの意義を持っているのである。そして、それを知ったとき、いま日本人は何をすべきなのか。きっとその答えが一人一人のなかに見えてくると思うのだ。
こんな体験を自分だけでしているのはいつももったいないと思っている。みなさんも世界にある、いま私たちに見えていない「日本」を探しにいきませんか?それは意外なほど簡単に見つかるし、日本のクリエイターたちがしてきたことはそれだけの意義を持っているのである。そして、それを知ったとき、いま日本人は何をすべきなのか。きっとその答えが一人一人のなかに見えてくると思うのだ。
J Pop Culture 見聞録←バックナンバー一覧はこちらから
JAPAN! JAPAN! JAPAN!←バックナンバー一覧はこちらから
執筆者:櫻井孝昌氏プロフィール
 作家、ジャーナリスト、事業企画・イベントプロデュース等の仕事とならび、世界23カ国延べ99都市で講演やイベント企画、ファッションショーといった「ポップカルチャー文化外交」活動を実施中。外務省委嘱のカワイイ大使プロデューサー、アニメ文化外交に関する有識者会議委員等も歴任。著書(発売順)に『アニメ文化外交』(ちくま新書)『世界カワイイ革命』(PHP新書)『日本はアニメで再興する』(アスキー新書)『ガラパゴス化のススメ』(講談社)『「捨てる」で仕事はうまくいく』(ダイヤモンド社)がある。
作家、ジャーナリスト、事業企画・イベントプロデュース等の仕事とならび、世界23カ国延べ99都市で講演やイベント企画、ファッションショーといった「ポップカルチャー文化外交」活動を実施中。外務省委嘱のカワイイ大使プロデューサー、アニメ文化外交に関する有識者会議委員等も歴任。著書(発売順)に『アニメ文化外交』(ちくま新書)『世界カワイイ革命』(PHP新書)『日本はアニメで再興する』(アスキー新書)『ガラパゴス化のススメ』(講談社)『「捨てる」で仕事はうまくいく』(ダイヤモンド社)がある。ツイッターでも海外情報発信中 http://twitter.com/sakuraitakamasa/
毎週水曜日更新!
※次回は瀋陽で開催された日本ファッションショーのオーディションの模様を
※次回は瀋陽で開催された日本ファッションショーのオーディションの模様を
 新型コロナウイルス感染症対策が各地で実施されています。イベント・店舗の運営状況は公式サイト等でご確認ください。
新型コロナウイルス感染症対策が各地で実施されています。イベント・店舗の運営状況は公式サイト等でご確認ください。

















